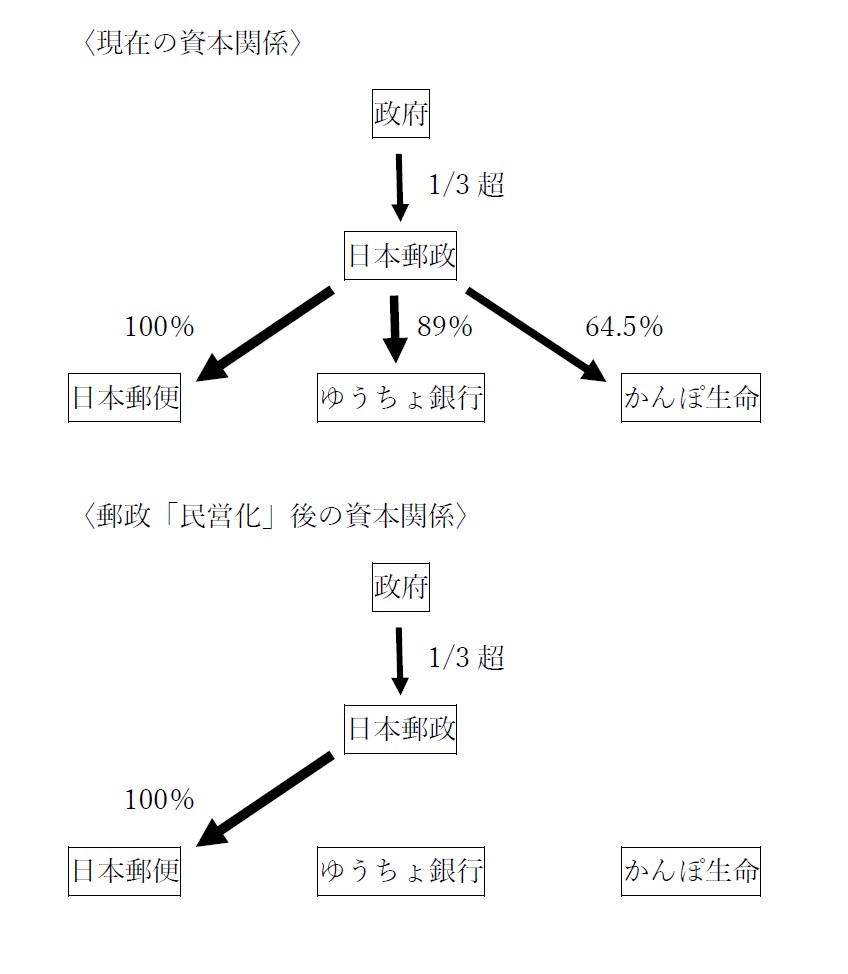前回まで3回のポスト(2月7日、2月16日、3月7日)で郵便局を舞台にしたかんぽ保険商品の不正営業事件について思うところを述べた。
そこでも簡単に触れたとおり、事件の過程で日本郵政は自らの不正営業問題が白日の下にさらされないよう、NHKに圧力をかけた。その際、NHK経営委員会が日本郵政の味方に付き、NHK会長に圧力をかけていたことが判明している。
これは「報道の自由」の崩壊を招く大問題だ。看過できない。
本ブログでもこの問題を取りあげようと思いながら手間取っていたところ、3月2日付の毎日新聞が「『番組の作り方に問題』 NHK経営委員長がかんぽ報道『介入』か 放送法違反の疑い」という記事を打った。
毎日新聞は昨年9月26日のスクープ以来、この問題の追及に熱心だ。毎日新聞の記事とNHK自身による検証記事を読めば、この問題の論点を追うことができる。
本ポストでは、遅ればせながら、私の意見を述べておきたい。
NHKのスクープと日本郵政の圧力
2018年4月24日――念のために言うが、2019年ではなく、2018年の話だ――、NHKのクローズアップ現代+は「郵便局が保険を“押し売り”!? 郵便局員たちの告白」という衝撃的なタイトルの番組を放映した。おそらく、郵貯グループの不適切営業に最初に切り込んだ番組だったと思う。これはアッパレだった。
7月になると番組側は続編を作るため、SNSで情報提供を呼びかけた。
これに対し、日本郵政、日本郵便、かんぽ生命が社長名でNHK会長宛に「内容が一方的で事実誤認がある」などと掲載中止を申し入れる。
この段階で既に郵貯内部で不適切営業は蔓延していた。
郵政側が「放送内容は間違っている」と思って抗議したのであれば、当時の3社長を含む経営幹部はよほどの無能か、裸の王様ということになる。
不正の存在を知りながら抗議したのであれば、もう背任に近い。
実態はおそらく後者であろう。日本郵政の鈴木・上級副社長は「圧力をかけた記憶は毛頭ない」と述べている。こういう時、本当に圧力をかけていなければ、「圧力をかけてなどいない」と言い切るもの。政治家の「記憶にございません」と同様、「記憶」という言葉を使って否定するのは後ろめたさの表れである。
日本郵政と手を組んだNHK経営委員会
ここまでは、「NHK」対「日本郵政」の戦いだった。
番組サイドが取材をやめないのに業を煮やした郵政側は、番組の担当者が『番組制作について会長は関与しない』と発言したことを問題視し、「放送法上、編集権は会長にあるはず。番組サイドの発言はNHKのガバナンス上、問題だ」とNHK経営委員会に訴えた。
日本郵政の言い分は、世間的には「言いがかり」の類いと言ってよい。
しかし、番組内容の真偽で争うと日本郵政にとって不利となるため、経営委から圧力をかけて現場を黙らせる、という手法を郵政側は選んだのだ。
(この戦術を考え出したのは、鈴木康夫・日本郵政上級副社長――郵政事業と放送行政の両方を所管する総務省の元事務次官――だった可能性がある。)
NHKの上田良三会長(当時)は常日頃、「我々は実際には、放送総局の方に分掌してやってもらっている。自主自律を堅持しながら、事実に基づいて、公平公正、不偏不党といいますか。そういう公共放送としての、守らなくちゃいけないスタンス。これをしっかり守るというのは、口を酸っぱくしてやっている。それを踏まえた上で、現場でやってくれ、と言っています」と表明していた。
番組内容が虚偽だったり取材手法に問題があったのならともかく、郵貯の不適切営業を取りあげた番組制作を止めなければならないとは、上田も考えていなかったに違いない。
だが、NHK経営委員会の石原進委員長(当時)や森下委員長代行(現委員長)から見れば、こうした上田の姿勢そのものに問題があった。
制作現場に任せ、政権批判をされては困る、ということだ。
石原は日本会議と関係があり、安倍政権と非常に近い。森下は安倍総理を囲む「四季の会」のメンバー。安倍が政権批判報道に神経を尖らせ、メディアに対して有形無形の圧力をかけてきたことは周知の事実である。
(脱線するが、石原を最初にNHK経営委員に任命したのは民主党政権(菅内閣)だった。「九州」枠で選ばれたと言うが、脇の甘さはこういうところにも表れる。)
こうして、戦いの構図は、「NHK」対「NHK経営委員会 + 日本郵政」に変わった。
(経営委員の全員が石原と森下に同調したわけではなさそうである。しかし、両名に反対して断固戦った者もいなかったようだ。NHK経営委の議事録的なものには、上田NHK会長に対する注意は、経営委員会の「総意」として行われたと書いてある。委員の一人でも頑強に抵抗すれば、この手の文書に「総意」という単語を載せることはできない。)
石原と森下は日本郵貯がつけた難癖に乗り、経営員会に上田を呼んで叱責した。
上田は抵抗するも、経営委員会には放送法に基づく「(NHK)役員の職務の執行の監督」権限があった。
2018年10月23日、NHK経営委員会は上田に厳重注意を行う。
立場上、上田も最後は経営委員会に逆らえない。最終的に上田は日本郵政側へ詫び状を出させられた。(実に子供じみている!)
こうした経緯を最初にすっぱ抜いたのが昨年9月26日の毎日新聞「NHK報道巡り異例『注意』 経営委、郵政抗議受け かんぽ不正、続編延期」という記事だった。
本来なら、石原や森下は自らの不適切営業を隠蔽したい郵政側を一喝し、NHKに対して「理不尽な抗議に屈するな」と激励する立場にあったはず。
だが、現実は違った。
2018年10月23日に行われた当該経営委員会の議事概要――当初、存在しないとされた――は、国会で批判されたことを受けて1年以上たった昨年11月1日に出てきた。
それは発言者が表に出してもよいと認めた発言のアウトラインであり、フルバージョンの議事録ではなかった。他の議題については発言者と発言内容がわかるのに、NHKのガバナンスに関する討議の部分だけ、発言者名が伏せられ、発言は極めて抽象的に要約してある。
議事概要には、議論の締めの部分だけ、「今回のことについて、いまだ郵政3社側にご理解いただける対応ができていないことについて、経営委員会として、誠に遺憾に思っている」という石原の具体的な発言が載せられている。
後段の「誠に遺憾」という発言を明らかにしたかったのだろう。だが、印象に残るのは、郵政に媚びへつらった前段の言葉遣いである。実に浅ましく、おぞましい。
11月13日の分の経営委員会に至っては、議事録の末尾に下記の文章が(昨年11月1日付で)追記されているのみだ。
○ NHKのガバナンスについて
平成30年11月7日付で、改めて日本郵政株式会社取締役兼代表執行役上級副社長より、NHK経営委員会宛に書状が届いたので、情報共有を行った。
会長に申し入れを行った内容のうち、本件の措置についての報告は求めないことを、経営委員会として確認した。
「情報共有」であって議論ではないから議事録は作りません、本件の措置については報告不要と確認したので議事録はありません、ということにしたかったのだろう。
こんな組織体が「NHKのガバナンス」を云々するとは、とんだ茶番である。
毎日新聞の記事が出ると、経営委員会による「放送現場への介入」という批判が(与党以外では)噴出した。
昨年10月11日、石原は国会に呼ばれ、「経営委員会は番組の内容や中身に立ち入ることは法律上禁止されている」という珍答弁を披露した。犯罪は法律によって処罰されるから、世の中に犯罪は起きない、と言っているのと同じだ。
この問題の追及に執念を燃やす毎日新聞は、この時の議事録に載っていなかった森下の言葉を取材によって復元した。それが冒頭で紹介した今年3月2日付の記事である。
毎日新聞によれば、2018年10月23日の経営委員会で森下は「郵政側が納得していないのは、本当は取材内容だ。本質はそこにあるから経営委に言ってきた」と述べていた。
森下は国会に呼ばれ、「いろいろと自由な意見交換をする中での言葉だったと思う」と自身の発言を事実上、認めた。
番組編集への介入があったことは明らかであり、これを見逃すのであれば、何が放送法違反になるのか、私にはわからない。
森下の釈明は、「具体的な制作手法について指示したものではない。経営委員が番組編集に関与できないことは認識している」というもの。
具体的な制作手法について指示しなければ、日本郵政を怒らせない内容の番組にしろ、というニュアンスを伝えても、番組編集への関与にならないとでも言うのか?
こんな人物が今、経営委員長に収まっている。しかも、二代続けて、だ。
報道の自由を取り戻すために
2019年6月27日、かんぽ生命は2014年以降に不適切な契約が約2万4千件あったと発表し、7月10日にはかんぽ生命と日本郵便が第三者委員会を設置して調査することを表明した。
日本郵政の幹部はNHKに蓋をすることには成功したかもしれない。しかし、腐敗の実態は隠そうとしても隠しきれないほど、巨大かつ醜悪だったである。
その後、7月31日にNHK(クローズアップ現代+)は「検証1年 郵便局・保険の不適切販売」というタイトルで続編を放映した。
今度は郵政側もさすがに抗議できなかった。2018年4月24日のクローズアップ現代+が間違っていなかったことも、事実によって証明されていた。
これを以って一件落着でよいのか? そんなわけがない。
一度大きく傷つけられた報道の自由を回復するためには、最低限、以下の三つのことを実現すべきだ。
第一は、森下俊三NHK経営委員長の解任。
その必要がないと言うのであれば、経営委は改ざんされていない議事録を公表し、毎日新聞の記事を否定すべきだ。
だが、先週3月5日に行われた衆議院総務委員会へ参考人として出席した森下は、議事録の公開を拒否した。
高市早苗総務大臣も、「より透明性を持った情報公開」を求めつつ、議事録公開を求めるところまでは踏み込まず。(そりゃあ、そうだろう。公開したら安倍のお友達を守れなくなる。)
一方、森下の発言については「現時点で放送法にただちに抵触するものではない」と庇ってみせた。
第二は、NHK経営委員会が上田NHK会長(当時)に行った厳重注意を取り消すこと。
日本郵便とかんぽ生命による大規模な不正営業の実態が明らかになり、クローズアップ現代+の番組が間違っていなかったことがわかった今も、2018年10月23日にNHK経営委員会が上田会長に対して行った厳重注意は取り消されていない。
これは「取材対象から抗議があった場合、NHK会長は取材対象の意向に沿うよう、番組制作上の指導を行うことが望ましい」と暗黙の裡に伝えたお達しが今も生きていることを意味する。
政権側から番組制作に関するクレームがあれば、NHK会長は時の権力者にご理解いただけるような対応をせよ、ということになりかねない。
昨年末、森下が石原の後任の経営委員長に選ばれた。ほぼ同時に、NHK会長には前田晃伸 元みずほファイナンシャル・グループ会長が就いた。前田も森下と同じく、四季の会のメンバーであった。
前田は就任時の会見で「どこかの政権とべったりということはない」と述べた。
だが、前田には、見かけによらず、食わせ者という評がある。件の厳重注意の趣旨を前田が体現し、「政権のためのNHK」にしないか、という危惧は少なからず残る。
そうした懸念を払しょくするためにも、根拠を失った――本当は最初から根拠などなかった――件の厳重注意は正式に撤回すべきだ。
最後に、NHK自身がNHK経営委員会の悪事を暴く検証番組を作り、世に問うこと。
報道の自由を守るためにある組織だと誰もが思っているNHK経営委員会が報道の自由を脅かした。その悪事を暴くことは報道機関であるNHKの務めであり、それを最もよく知る立場にあるのはほかならぬNHKである。
NHK自身にも、表に出したくない脛の傷がまったくないわけではないのかもしれない。クローズアップ現代+は、経営委員会による会長への厳重注意が番組制作へ影響したのではないかという疑念について、以下のように否定している。
去年(2018年)10月23日に、経営委員会が会長に行った厳重注意が、放送の自主・自律や番組編集の自由に影響を与えた事実はありません。前述のとおり、動画の更新作業や取材継続の判断は、去年(2018年)の7月から8月にかけて行われたものです。したがって、経営委員会による会長への厳重注意が番組の取材や制作に影響したことは時系列からみてもありえません。
しかし、これを額面どおり受け取ることはできない。
2018年7月から8月にかけて下した、取材継続をやめるという判断に日本郵政側の圧力は影響していなかったのか?
経営委員会による会長への厳重注意がなければ、クローズアップ現代+の続編放映は2019年7月ではなく、もっと早かったのではないか?
日本郵便とかんぽ生命の不正営業があまりに巨大であり、しかも、NHKは取材を通じてそれをいち早く察知していた。
続編が放映されて世間の関心が高まれば、日本郵便とかんぽ生命に騙される人は減ったはずであり、そのことはNHKの制作現場も痛いほど感じていたと思われる。
続編の放映が最初の番組放映から1年3ヶ月も後になった理由が「郵政のテーマを続編として深めて取り上げるには十分な取材が尽くされていなかったため」だと言われ、はいそうですか、と信じるほど世間は馬鹿じゃない。
NHKの制作現場は、悪いのはNHK経営委員会(特に石原と森下)だと思っていることだろう。それはほとんど正しい。
だが、その悪だくみを叩くことを毎日新聞任せにしている現状は、NHK側の落ち度だ。前田や幹部連中が押さえつけているのだろうか?
NHKが「経営委」化し、権力の犬になることだけは何としても避けなければならない。
NHKは今月1日から、ネット同時配信サービスを試験的に始め、4月には本格サービスへと移行する。受信料制度の抜本的な見直しも俎上にあがっていると言う。
NHK経営委員会を含めた広い意味でのNHKグループには、その前にやるべきことがある。自ら身をただすことだ。