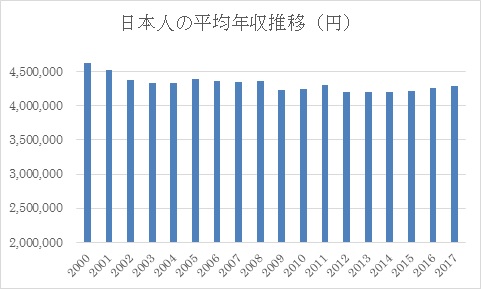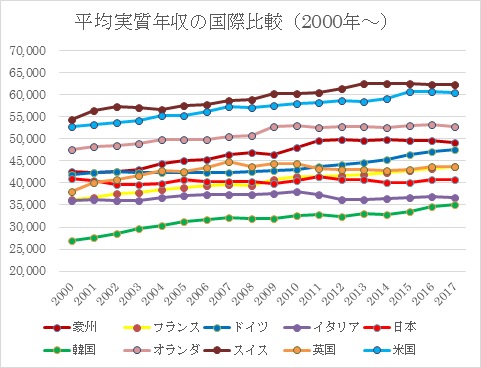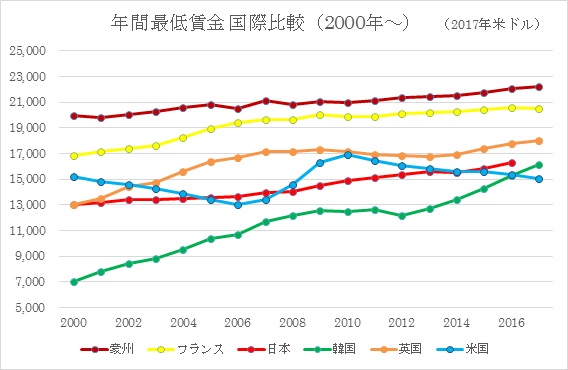1月31日、日本郵政、日本郵便、かんぽ生命の3社は監督官庁(金融庁と総務省)に業務改善計画を提出した。昨年末に業務停止及び業務改善命令を出され、1月末が改善計画書を提出する期限だったのである。
かんぽ保険商品の販売に際して日本郵便とかんぽ生命で不正営業が行われたことは、今や知らない者はない。しかし、昨年12月18日に特別調査委員会が出した調査報告書を読んでも、どんな不正がどれほどの規模で行われたのか、全体像は明らかにならない。先日、業務改善計画書が出された際に追加報告がなされたが、それも不正の全容解明と言うにはほど遠い。「トゥー・リトル、トゥー・レイト」が続いている。
確かに、3人の社長(長門正貢日本郵政社長、横山邦夫日本郵便社長、植平光彦かんぽ生命社長)と日本郵政のドンと言われた人物(鈴木康夫上級副社長)は辞職した。しかし、それも見ようによっては「逃げ得」と言える。
不祥事が起こるたびに繰り返し言われるのが「真相解明」「責任追及」「再発防止」という言葉。本来、最大の再発防止策は厳格な責任追及、すなわち責任者の処罰である。だが、責任を追及するには不正の真相解明が大前提となる。今回の不祥事では、上記が三位一体で曖昧なままに放置されている。
日本郵政グループは、郵便、貯金、保険を生業とするが、儲けの中心は金融業。金融業は信用を旨とする。それを失ったままに総括を終わらせるのであれば、日本郵政に金融業を続ける資格はもはやない。
本ブログでは、日本郵政グループの不正営業――日本郵政や日本郵政に忖度するメディアは「不適切」営業と呼ぶようだが、それに付き合うつもりはない――を私なりの視点で点検してみたい。
罷り通った不正、続く過小評価
日本郵政グループにおける不祥事の根本は単純だ。グループ各社で「顧客だまし」の不正営業が――おそらく長年にわたって――横行していたことである。
「かんぽ保険」及び(かんぽと委託契約を締結した)「日本郵便」では、高齢者など顧客に嘘の説明をしたり、顧客の支払い能力や年齢による制約を無視したりしながら、多額の保険商品が詐欺まがいの手法で販売されてきた。詳しくは郵政側が行った調査報告書(昨年12月18日)や業務改善計画書(今年1月31日)を参照してもらいたいが、これがまたわかりにくい。昨年12月27日付で金融庁が行政処分を下した際の「Ⅱ.処分の理由」を読む方が遥かに手っ取り早いだろう。もっと具体的に不正のイメージを掴みたければ、NHKや西日本新聞の特集を見ることをお勧めする。
「かんぽ生命保険契約調査 特別調査委員会」の調査報告によれば、2014 年4月から2019年3月までの間に、法令又は社内規則に違反する疑いのある保険契約が1万2,836 件あった。そのうち、2019年12 月15 日現在で、法令違反と認められた事案(不祥事件)が48 件、社内規則違反と認められた事案 (不祥事故)は622 件にのぼった。こうした不正に関与した募集人――個人向け保険販売のほとんどは日本郵便(郵便局)の募集人に行われている――の数は、少なくとも5,797人に及んだ。(先月31日の発表では、不祥事件は 106 件、不祥事故は1,306 件に膨らんでいる。)
不正そのものを示すわけではないが、保険の新契約について顧客から苦情が寄せられた割合も、郵政の数字は他の民間保険会社と比べて異常に高い。民間4社は2017年で0.42%、2018年で0.32%なのに対し、郵政はそれぞれ2.15%と1.46%。郵政の保険営業では、顧客から苦情が来る比率が民間他社に比べて5.1~4.6倍も多い、ということだ。
この数字を見て、郵政は金融機関として「終わっている」と思うのは私だけだろうか。
しかし、郵政が行っている調査の本当の問題は、「これでは調査になっていない」ということである。こんないい加減な内容を恥ずかしげもなく調査と称して出してくるとは・・・。唖然とするほかない。
第一に、特別調査委員会は「氷山の一角」しか調査する気がない。同委員会が投網をかけたのは「顧客から苦情のあった契約」が中心だった。顧客が騙されたことに気づいていない契約は「不正の疑いがある」案件にならない。
昨夏になって郵政は過去5年分の全契約約3千万件の調査に取り組むと発表した。だが、約1,900 万人の顧客のうち、今年1月28日時点で回答があったのは約 100 万通にとどまる。お年寄りをはじめ、金融商品の説明など、よくわからない人も少なくない。また、おかしいと思っていても様々な事情から――例えば、家族に知られたくないとか、(特に田舎では)地域における郵便局の募集人との関係を慮ったりするとか――苦情を申し立てない人もいるだろう。
1月31日の記者会見で日本郵政の増田社長は全件調査に触れて改革姿勢をアピールしようとしていた。しかし、増田が述べたのは結局、「顧客の気付きを促す」取り組みでしかない。今後もあくまで顧客からの申し立てに基づいて調査を進めるつもりのようだ。
それだけではない。調査期間が過去5年間に限定されているのは何故なのか、についても納得できる説明はない。ゆうちょ銀行と日本郵便による投資信託の不正販売調査が中途半端なものに終わってしまった。郵政グループの調査は、どこまで行っても不正の実態を過小評価し続けるだろう。
第二に、郵貯側が不正の疑いがあるとした案件(=顧客から苦情が寄せられた案件)のうち、アウトと判定されたのは、募集人が「自認」したものだけだった。これまた、開いた口がふさがらない。募集人が不正を働いていたとして、不正を働いたかと聞かれて正直に「やりました」と認めるケースよりも、認めないケースの方が圧倒的に多いだろう、ということは容易に想像がつく。
警察や検察は自白がなくても他の証拠があれば逮捕・立件するし、裁判でも自白なしで有罪の判決が下ることは十分にあり得る。「自白しなければ無罪」という判定がまかり通るのは、もたれあいの蔓延した郵政一家の中だけである。
さすがに金融庁も切れたと見える。行政処分を下した際に「事故判定やその調査において、顧客に不利益が生じている場合であっても、契約者の署名を取得していることをもって顧客の意向に沿ったものと看做し、募集人が自認しない限りは事故とは認定せず、不適正な募集行為を行ったおそれのある募集人に対する適切な対応を行わず、コンプライアンス・顧客保護の意識を欠いた組織風土を助長した」と郵政側を厳しく批判している。
金融庁から行政処分を解いてもらうためには仕方ない、と考えたのだろう。郵政側も業務改善計画書には「自認に頼らない事実認定・事故判定の実施」という文言を入れてきた。だが、どこまで本気で取り組む気があるのか? これまでのゴマカシ体質を考えれば、俄かには信用できない。
現場の責任――どこまで処分されるか?
業務改善計画書によれば、郵政側はガバナンスの改善など、様々な不正の再発防止策を(金融庁などの指示をなぞる形で)講じることにしている。だが、この種の不祥事が起きた時に最も有効な再発防止策は、責任の所在を明らかにして厳格な処罰を行うことだ。それがなければ、どんなに模範解答的な文言を連ねても、「仏作って魂入れず」である。
業務改善計画では、保険募集人と(現場の)管理職の処分については、総論として以下のとおり言及されている。
① 募集人処分における「業務停止」及び「注意」の追加
募集人処分については、従前は「業務廃止」と「厳重注意」の二段階としておりましたが、一定期間募集を停止させる処分等を追加し、不適正募集の態様・程度に応じた処分を実施します。
② 管理者に対する処分
不適正募集を発生させた募集人の管理者については、部下社員の過怠の程度に応じた厳格な処分を日本郵便に対して要請します。
業務廃止と業務停止の違いを含め、抽象的でよくわからない、というのが正直なところだ。不正営業の主な舞台となった日本郵便は、「懲戒処分運用」という項目を設けてもう少し具体的に書いている。
(ア) 特定事案調査等の結果に基づく処分
特定事案調査の結果に基づき、非違の認められた社員及び管理者に対しては、厳格な処分を実施します。かんぽ生命と連携し、不適正募集を発生させた募集人や募集態様に課題がある募集人に対する研修カリキュラム等を策定し、募集再 開に向けた研修を実施します。
(イ) 管理者に対する処分
全ての金融関係管理者を「保険募集品質改善責任者」に指定し、その役割を明確化した上で、過怠があった場合に厳格な処分を実施します。
そもそも、不正の全容がはっきりしないままで適切な処分などできるのか、という疑問がある。
しかも、この前段には、募集人が自らの違反行為を申告したり、調査への十分な協力を行ったりした場合には、募集人に対する処分を本来よりも軽減又は免除する、といった司法取引まがいなことまでさらっと書いてある。それくらいしないと不正を発見できないという情けない話の裏返しなのであろう。だが、「免除」はありえない。「処分の厳格化」が聞いてあきれる。
民間の金融機関と異なり、郵政グループは政治や行政と密接につながっている組織だ。
旧特定郵便局長会は今も自民党の集票マシーンとして動き、2019年の参議院選挙では柘植芳文(前職は全国郵便局長会会長)、2016年の参議院選挙では徳茂雅之(前職は全国郵便局長会相談役)を自民党でトップ当選させた。
郵政グループの組合(JP労組)も難波奨二と小沢雅仁の二名を立憲民主党から参議院議員として国会に送り込んでいる。
日本郵政グループは経営幹部に旧郵政省の流れを汲む総務省OBを受け入れてきた。
昨年の配置は、日本郵政が鈴木康夫上級副社長(元総務次官)、かんぽ生命が千田哲也代表執行役副社長(旧郵政省出身)、ゆうちょ銀行が田中進副社長(旧郵政省出身)、日本郵便が衣川和秀(旧郵政省出身)と要所を抑えていた。
1月6日から始まった新体制も、日本郵政の新社長には増田寛也(旧建設省出身、元岩手県知事、元総務大臣)を迎え、日本郵便は衣川、かんぽ生命では千田がそれぞれ昇格して新社長に就いた。
日本郵政グループが政治にも行政にも政治力を働かせられることは、グループ内の人脈構成からも明らかだ。果たして身内に厳しい処分を科すことができるのだろうか?
ノルマが生んだ不正。それを放置した罪
それでも、募集人や現場の管理職に対し、最低限の責任追及と処分が行われることになろう。では、経営陣に対してはどうか? こちらは、逃げ切る可能性がかなりありそうだ。
金融庁は、日本郵政グループによる不正営業が行われた理由として、①過度な営業推進態勢、②コンプライアンス・顧客保護の意識を欠いた組織風土、③脆弱な募集管理態勢、④ガバナンスの機能不全、という四点を指摘している。ごく大雑把に言えば、①は「行き過ぎたノルマ営業の横行」ということであり、②から④は「広義のガバナンス欠如」に関係している。
ちなみに、金融庁の指摘は、法令順守やコンプライアンスの観点から不正営業の蔓延を問題視したものだ。しかし、日本郵政グループ経営陣の責任は、ビジネス面でも格段に重い。
いつからかも定かでないが、日本郵政グループでは目先の収益を追って不正営業が生まれた。悪事が大規模に行われれば、世間に漏れる。その結果、昨年7月にはかんぽ商品の販売を自粛(当初は8月末まで、その後年内一杯に延長)し、昨年末には3ヶ月間の業務停止処分まで食らった。収益上のマイナスは相当なものになろう。
何よりも、日本郵政グループは長年培ってきた世間の信用を失った。不祥事の発覚以来、株価も大きく下げている。
金融庁・総務省から処分を受けようが受けまいが、十分に大きな経営責任がある、と考えるのが普通の感覚というものだ。
過剰なノルマ営業について金融庁は、「営業目標として乗換契約を含めた新規契約を過度に重視した不適正な募集行為を助長するおそれがある指標を使用し続けた上に、経営環境の悪化により、営業実績が振るわないことが想定されるにもかかわらず、具体的な実現可能性や合理性を欠いた営業目標を日本郵便とともに設定してきた」と指弾している。
モーレツ営業で知られる住友銀行(現在は三井住友銀行)から日本郵便社長に転じた横山がノルマ営業を進めた、という指摘もあるようだ。
昔は郵便局員が国家公務員だった流れを汲む日本郵政グループの職員とモーレツなノルマ営業で知られた住友銀行員では、能力もモラルも違いすぎる。しかも、このところ低金利が続いて金融機関の収益環境は最悪、保険商品も売りにくい。
いくら高いノルマを課されても、現場で目標を達成できない事態が起きたとしても不思議はなかった。
いずれにせよ、無茶な目標が不正営業を生んだことは、一流銀行のバンカーだった横山にとって想定外のことだったに違いない。
私は、ノルマ営業が全否定されるべきだとは思わない。だが、それが不正を生んだところで横山たち経営陣は目標を見直すべきだったし、不正の根絶に向けて果断な対応を行うべきだった。
それをしなかった(できなかった)時点で横山のバンカーとしての倫理観は失われ、日本郵政のガバナンス崩壊に直結する責任を負い始めることになったのだと思う。
経営「無責任」の明確化
日本郵政で行われた不正営業の責任は、郵便局の募集人や(中間)管理職だけを処分すれば済む、という問題ではない。それは金融庁もよくわかっていると見える。行政処分を下した際、いの一番に「今回の処分を踏まえた経営責任の明確化」を求めた。
しかし、日本郵政側はその指摘を本当に深刻に受け止めているのだろうか? 1月31日付で提出された業務改善計画書(要旨)の末尾には、短く次のような記述がある。
今般の事態を招いた責任を明確化するため、日本郵政、日本郵便およびかんぽ生命の代表執行役社長等が辞任するとともに、役員の月額報酬の減額等を実施しました。
実にあっさりしている。「処分」という言葉も見当たらない。しかも、完了形だ。
今年1月5日に辞任したトップとは、日本郵政の長門(前職=シティバンク銀行会長)、かんぽ生命の植平(前職=東京海上ホールディングス執行役員)、日本郵便の横山(前職=三井住友銀行社長)の三名。さらに、「郵政のドン」とも言われた鈴木康夫日本郵政上級副社長(元総務省事務次官)も退いた。
彼ら4名の退任を以ってこの間の経営陣の責任を明確化する、というのはゴマカシ以外の何物でもない。グループ各社で役員を務めていた者の多くは留任し、昇格する者すらいる。
例えば、日本郵便の衣川新社長は日本郵政の専務執行役からスライド昇格を果たした。かんぽ生命の千田新社長が同社副社長から昇格したことは前述のとおり。日本郵便代表取締役副社長の米澤友宏上級副社長(金融庁出身)と執行役員副社長の大澤誠(元全国郵便局長会会長)は留任した。かんぽ生命代表執行役副社長の堀金正章(郵政省出身)も留任だ。全部は調べていないが、ざっとこんな具合である。
彼らが前体制の下で日本郵政グループの不正営業問題に関わっていなかった、なんてことはありえない。それでも出世しているんだから、「経営責任の明確化」ではなく、「経営責任をとらないことの明確化」だ。
役員の月額報酬を減額した、というのも意味がよくわからない。
報道によれば、2020年1月から6月までの半年間、代表執行役副社長や専務執行役(内部監査担当、コンプライアンス担当)の月額報酬の30%を減額し、常務執行役(経営企画担当)やその他の専務執行役、常務執行役なども5~20%減らす。かんぽ生命と日本郵便も副社長の月額報酬40%を削減するほか、その他の執行役も5~30%カットするという。
上記がすべてであれば、先般辞職した3社長や鈴木上級副社長はノー・ペナルティということになる。衣川や千田も同様だ。
これだけ大きな問題を起こしておいて、行政処分を受けるまで自らの役員報酬に手をつけてこなかったなんて、厚顔無恥にもほどがある。
経営陣が「知らなかった」は通らない
なぜ、こんなことがまかり通るのか? 経営陣を守るために使われているのが「だってボク、知らなかったんだもん」というロジックである。
辞職した長門正貢社長(日本郵政)は保険商品の不正販売を認識した時期について「郵政の取締役会で議論したのは(2019年)7月23日が初めてだ」と述べている。「(日本郵政の)取締役会に全く情報が上がってきていなかった」「現場から情報が上がってこないことには話が始まらない」とも不平を漏らした。
これだけ巨大な膿を伴う問題が長年にわたって起きていたのだ。長門たちが去年の夏まで問題をまったく認識していなかった、などというのは与太話にしか聞こえない。(万一真実なら、そんな無能な経営陣は全員クビだ。)
かんぽ商品の不正営業問題については、2018年4月24日にNHKの「クローズアップ現代+」が『郵便局が保険を“押し売り”!? 郵便局員たちの告白』という番組を放映し、大きな話題を呼んだ。
仮に郵政に鈍い経営者ばかりが集まっており、現場から悪い情報が上がってきていなかったのだとしても、遅くともこの時点では気づかなければならなかった。
2019年9月30日の会見でこの点を突かれ、長門は次のように答えている。
(2018年)4月24日の「クローズアップ現代(+)」、あれと、それから今年また2回目を放送されました。2回とも、昨日あらためて再び拝見させていただきました。おっしゃってる点は、今となってはまったくそのとおりだなと思っておりまして(略)。
今から見ればなんだったの、っていう議論はあると思いますけれども、(番組や意見募集のSNS広告が)やっぱり詐欺とか押し売りとか内部資料なんてとかっていうことで、これはちょっとひどいんじゃないか。みんなで議論して、みんなで思って、今から思うと少し不遜だったかもしれませんけれども、我々はこんなに募集品質問題、頑張ってきていて、ここまで成果があって、こんな成果が出てきて頑張っている最中なのに、僕らが悪のドクロ仮面のように、悪の権化かのようにワーッと言われるのはトゥーマッチじゃないか、という意見が出てきたので抗議しようというので抗議(した)。
前半については失笑するしかない。
その一方で下線部の発言は、遅くとも2018年夏の時点で日本郵政が「募集品質問題」に取り組んでいたことを意味する。募集品質問題とは保険の不正営業問題を郵政内部でそう呼んでいたのであろう。
2019年7月まで経営幹部が不正営業の実態を認識していなかった、というのは嘘だと長門自身が告白しているわけだ。
郵政の経営陣は、この時点で既に不正営業問題を把握していた。だからこそ、番組を見て恐慌状態に陥ったと考えれば、納得がいく。結局、彼らはNHKの番組を奇貨として不正の是正に奔走するどころか、こともあろうにNHKに圧力をかけ、続編の制作と放送を止めさせようとしたのである。(この点については、本ブログで近いうちに取り上げるつもりだ。)
長門が「知らなかった」と言ったのには、自分たちの経営責任を免れるということ以外にも理由があった。
日本郵政グループは、2019年4月にかんぽ生命の株式を売り出している。その後、不正営業の問題が表面化してかんぽ生命の株価は大きく下落した。株式売却よりも前に不正営業のことを知っていて公表しなかった、ということになれば、長門たちは損失を被った株主から訴えられてしまう。
日本郵政の新経営陣は、辞任した4人の社長たちへの退職金支払いをどうするのだろうか?
また、昨年以前に受け取った報酬について役員たちに返還を求めることもしないのだろうか?
それを見れば、増田新社長がお飾りかどうかがわかる。
お咎めなしか、形ばかりの追加処分しか出てこなければ、日本郵政グループの腐りきった体質は今後も変わらない、ということだ。
日本郵政による「経営責任の明確化」を金融庁が今後どう判断するかも要注目である。(日本郵便とかんぽ生命に対して監督上の命令を出しているものの、郵政と腐れ縁の総務省には期待しても仕方がない。それでも、金融庁が突っ張れば、総務省だけがお茶を濁すというわけにはいくまい。)
金融庁は昨年末の行政処分ではそれなりにケジメを示した。しかし、郵政グループへの立ち入り検査に入ったのは昨年9月だ。「初動の鈍さ」を指摘されても仕方がない。
郵政グループに巣食う既得権益の塊――旧特定郵便局長、組合、旧郵政官僚など――は必死に生き残りを画策するはずだ。旧特定郵便局長会などは政治を動かして金融庁に圧力をかける可能性がある。かんぽ生命等の株式を追加売却して財源確保に充てたい財務省も弟分の金融庁に手を回し、軟着陸を求めるかもしれない。
だが一方で、この問題に毅然とした対応を貫けなければ、金融監督機関である金融庁は内外で信用と権威を失ってしまう。ここは金融庁の矜持に期待するしかない。
金融庁までもが日和ってしまうようなことがあれば、日本郵政グループ経営陣の責任を問うために残る方法は、株主代表訴訟くらいだ。
郵政の不正は、内部から正すには巨大すぎ、腐りすぎ、広がりすぎている。