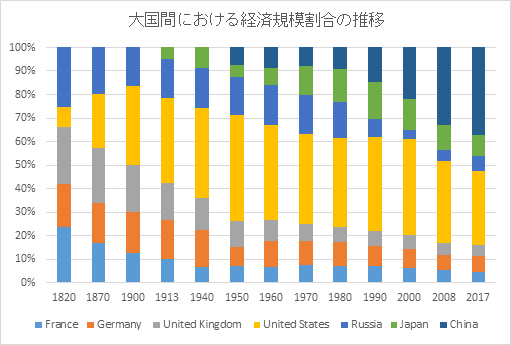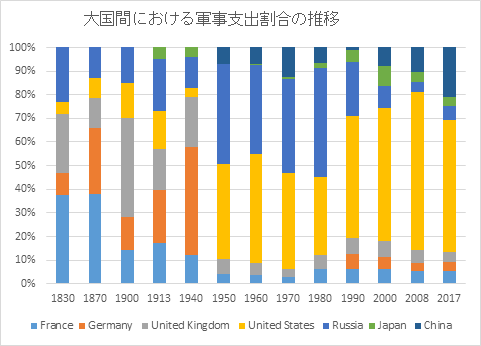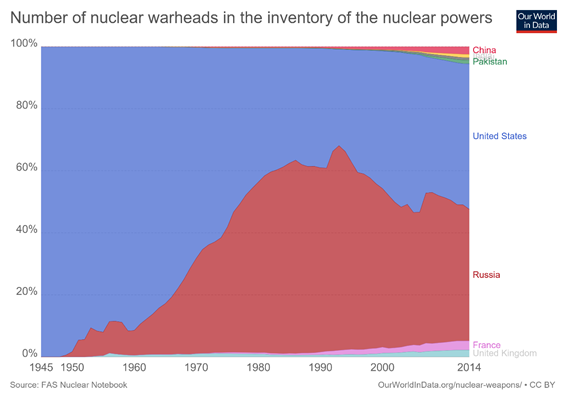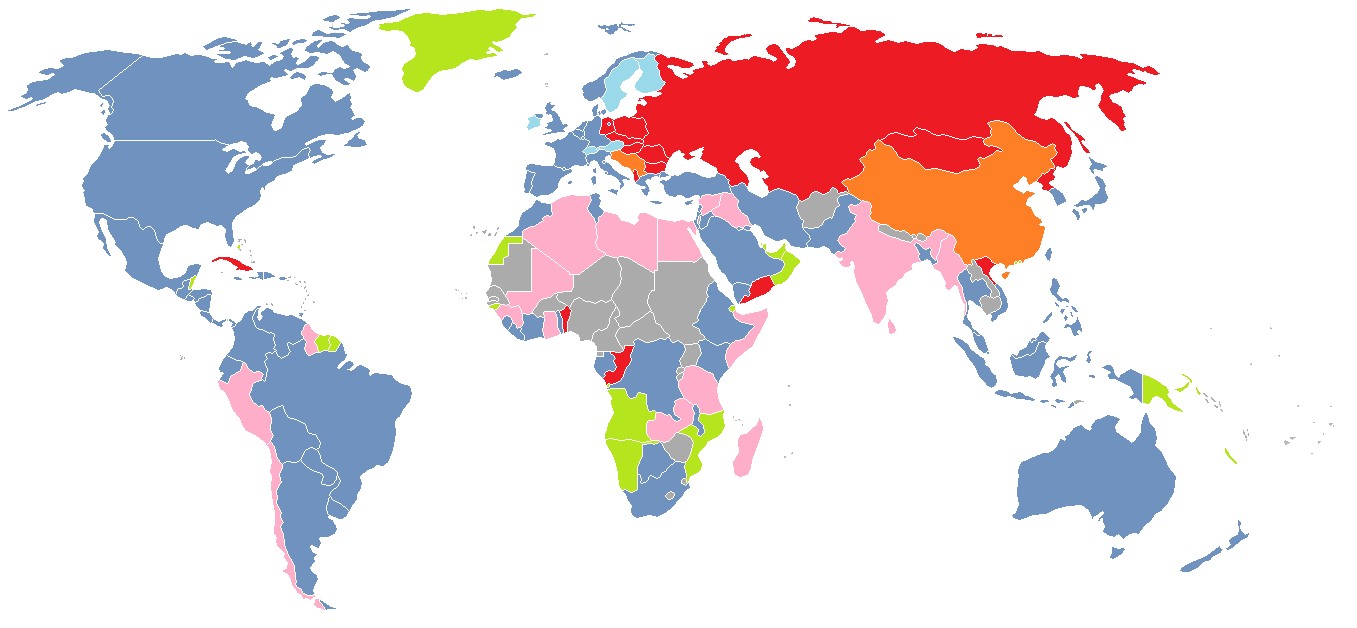少し前の話になるが、5月25日から28日まで、新天皇が迎える最初の国賓としてドナルド・トランプ大統領が日本を訪れた。それからほぼ一週間後、トランプは国賓待遇でエリザベス女王に招かれ、訪英している。
日本と英国でトランプを迎えた両国民の態度は随分違って見えた。少なからぬ英国人はトランプの訪問を歓迎しなかった。ロンドンでは数千人規模でトランプに抗議するデモが行われ、ガーディアン紙は「トランプはデマゴーグ(扇動家)であり、歓迎しない」と突き放した。
一方、日本でのトランプは、天皇陛下との会見や日米首脳会談といった「真面目な」政治日程だけでなく、ゴルフ、大相撲観戦、炉端焼きなどの「軽い」イベントによってテレビや新聞などを完全にジャックした。(傍らには選挙目当てでトランプに寄り添う安倍晋三が微笑んでいた。)メディアも野党も、安倍の「過剰接待」を批判することはあっても、トランプその人を非難する素振りは見せなかった。日本人がトランプを見る目も、概して温かかった――少なくとも、厳しくはなかった――ように思われた。
昨春行われた米国ピュー・リサーチの調査によれば、国際政治面でトランプ大統領を信頼できると答えた日本人の比率(30%)と英国人のそれ(28%)の間に大差はなかった。一つ考えられるのは、日本人が過去一年間でトランプに対して好意を持ち(トランプに対する反感を和らげ)はじめたということ。上記調査の2017年と2018年の数字を比べれば、その萌芽を読み取れないこともない。
<米国大統領が国際政治面で正しいことをしている、と思う人の比率>
| 2016年(オバマ) | 2017年(トランプ) | 2018年(トランプ) | |
|---|---|---|---|
| 日本 | 78% | 24% | 30% |
| 英国 | 79% | 22% | 28% |
| ドイツ | 86% | 11% | 10% |
| フランス | 84% | 14% | 9% |
| カナダ | 83% | 22% | 25% |
| 韓国 | 88%(2015年) | 17% | 44% |
各国とも数字はオバマ政権末期から急落している。だが、ドイツやフランスではトランプ大統領の就任2年目となる2018年にもさらに低下しているのに対し、日本ではやや持ち直している。なお、韓国の数字がトランプ2年目で跳ね上がっているのは、米朝首脳会談によって米朝関係が最悪期を脱したことの影響と思われる。
本稿では、日本人がトランプに抱く「好意」の理由について考える。(特に明記しない限り、米国や米国大統領に対する諸外国の評価に関する数字はピュー・リサーチの調査を、米国内での大統領支持率についてはギャラップ社の調査を使用した。)
反国際協調の不人気と政権持続可能性
米国大統領に対する日本人の信頼は、当該大統領が国際主義に背を向ける場合に明らかに低下するほか、当該大統領の国内的な権力基盤が失われた際にも低下する傾向が見てとれる。
例えば、単独行動主義(ユニラテラリズム)を掲げたブッシュ・ジュニア。2011年の同時多発テロ後、ブッシュの支持率は9割近くまで急騰した。しかし、二期目に入いると支持率が5割を超えることは基本的になく、政権末期には3割前後まで下がってレイムダック(死に体)化した。「ブッシュ大統領は国際政治で正しいことをしている」と答えた日本人の比率も、2006年は32%、2007年は35%と低水準で、支持率が3割を切った2008年には25%にまで下がった。(2004年以前の数字は不明。)
バラク・オバマ大統領は――客観的にみると、国際的な責任に背を向けた国内重視の姿勢が目立ったのだが――、単独行動主義を標榜したブッシュの後任であり、イラクからの米軍撤退を進めたということを以って、日本では国際協調を重視した大統領とみなされた。その結果、就任1年目と3年目には日本人の8割以上が「オバマ大統領は国際政治で正しいことをしている」と答えた。就任当初6割を超えていたオバマの支持率は、2年目に入ったころから5割を切って低迷するようになる。オバマ大統領を評価する日本人の比率も、2014年には60%まで低下した。
トランプはどうか? 「アメリカ・ファースト」を唱えるトランプの政策や行動スタイルは、国際協調主義とは対極にあると言ってもよい。大統領支持率も、2017年1月の就任時で45%。いわゆる「ハネムーン」期間のご祝儀もなく、その後、同年夏から年末にかけ、支持率は35%近辺まで下落した。しかも、この頃は「ロシア疑惑で弾劾されれば、任期途中で辞めざるを得なくなる」という見方も少なくなかった。2017年に「トランプ大統領は国際政治で正しいことをしている」と考える日本人の割合は24%しかなく、オバマ政権末期の78%から急落したばかりか、ブッシュ政権末期の数字さえ下回る。
ところがその後、トランプは意外なしぶとさを見せる。米国内での支持率は底割れすることなく、2018年の春頃から徐々に上がった。ロシア疑惑の一応の終結や経済の拡大などを背景にして、今年4月段階では46%と就任以来の最高を記録した。(と言っても50%に届かない低水準ではあるが・・・。)先月末に行われたCNNの調査でも、トランプが再選されると思う人の割合は54%、負けると思う人は41%だった。
「日本は特別」という意識~日本叩きは比較的温い
トランプ大統領は就任以来、イスラエルを除く世界中の国々と摩擦や対立を引き起こしてきた。そして、自国に厳しい態度をとる国やその指導者に対して当該国民が好意を抱かないことは当然である。ピュー・リサーチの調査では、移民問題やNAFTAでトランプから目の敵にされているメキシコでは、「米国大統領が国際政治面で正しいことをしている」と答えた比率は2017年で5%、2018年も6%にすぎない。2015年(オバマ大統領)の49%から大幅に下落した。トランプからNAFTAや関税問題でやり玉にあげられたカナダでも、2018年における上述の数字は25%となり、2016年(83%)から58%も下がった。逆に、トランプが唯一肩を持つイスラエル国民の69%は、2018年段階で「トランプは国際政治面で正しいことをしている」と高く評価した。オバマ政権がイスラエルに冷淡な態度をとった2015年には、この数字は49%まで低下していた。
日本はどうか? もちろん、2018年3月に発動された鉄鋼・アルミ追加関税は日本企業にも適用されたし、現在、日米間で物品貿易協定(TAG)交渉が行われていることは周知の事実である。しかし、これまでのところ、日本はトランプのあからさまな「標的」となっていない。同盟国の中では、前述のメキシコやカナダはもちろん、欧州諸国に比べても日本への圧力は少ない方だ。
日本がトランプから「大喧嘩を仕掛けられる」ことを免れる一方で、トランプは日本人が嫌いな国に対してそれこそ「大喧嘩を仕掛ける」ようになった。具体的には、北朝鮮と中国である。
「敵の敵は味方」に通じる感覚~日本人が嫌いな国を叩くトランプ
〈北朝鮮〉
北朝鮮は日本人が最も嫌っている国、と言ってよいだ。諸外国に対する日本人の意識を問う調査としては、内閣府の「国際問題に関する世論調査」が有名である。だが、同調査には北朝鮮について敢えて好感度を問う設問がない。少し探してみたら、今年1月21日に日本経済新聞が発表した世論調査で北朝鮮に対する友好意識を尋ねていた。その結果は、「好き」「どちらかといえば好き」という回答が0%。「どちらかといえば嫌い」が12%、「嫌い」が71%であった。
その北朝鮮に対し、トランプ政権は「最大限の圧力」を標榜し、軍事的先制攻撃を排除しない姿勢を示す一方で中国などを巻き込む形で経済制裁を極限まで強化した。北朝鮮も核・中長距離ミサイルの実験を繰り返したため、2017年末から2018年初めにかけては米朝軍事衝突が起きても不思議ではないと思われるほど緊張が高まる。しかし、その後急転直下、2018年6月にシンガポールでトランプと金正恩が会談。そのあたりから、北朝鮮は核実験と中長距離ミサイルの発射を控えることになった。米国の方は北朝鮮攻撃も辞さない姿勢を見せなくなった一方、金正恩が求める経済制裁の緩和には応じていない。(ただし、中国や韓国、ロシアなどの制裁破りについては、ある程度多めに見ているような印象である。)
多くの日本人の目には、トランプは日本人が脅威と感じる北朝鮮から核実験やミサイル発射のモラトリアムを引き出す一方で、日本人が大嫌いな北朝鮮に対して今も経済制裁を緩めず圧力をかけ続けているように見える。しかも、昨年春以降、それまであった戦争前夜のような重々しい雰囲気は遠のいている。誤解を恐れずに言えば、現在の米朝関係は多くの日本人にとって「ほど良い」緊張にある。
どの程度本気かはわからない――おそらく、日本政府に貸しを作るくらいのつもりなのだろう――が、トランプは拉致問題への言及も忘れることがない。その面でも、多くの日本人の目には、バッド・ガイではなく、グッド・ガイに映っている。
〈中国〉
日本にいると、中国は危険な存在という見方が支配的だ。しかし、ほかの国でも中国が日本同様に嫌われているわけでは必ずしもない。下記のピュー・リサーチによる調査が示すとおり、欧米市民の対中観はおおまかに言って二分されている。
中国に対する好感度
(上段は2018年春、カッコ内は2010年の数字。ただし、カナダのカッコ内は2009年の数字)
| とても好き | やや好き | やや嫌い | とても嫌い | |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 2% | 15% | 48% | 30% |
| (2%) | (24%) | (49%) | (20%) | |
| 米国 | 5% | 33% | 32% | 15% |
| (10%) | (39%) | (24%) | (12%) | |
| カナダ | 6% | 38% | 32% | 13% |
| (8%) | (45%) | (27%) | (11%) | |
| 英国 | 10% | 39% | 24% | 11% |
| (8%) | (38%) | (26%) | (9%) | |
| ドイツ | 3% | 36% | 46% | 8% |
| (2%) | (28%) | (46%) | (15%) | |
| フランス | 4% | 37% | 36% | 18% |
| (6%) | (35%) | (35%) | (24%) | |
| 韓国 | 2% | 36% | 50% | 10% |
| (1%) | (37%) | (46%) | (10%) |
この表を見れば、中国嫌いという点において日本は世界でもトップクラス、ということがわかる。
その中国に対し、トランプは就任2年目の昨年あたりから照準を定めるようになった。2018年3月の鉄鋼・アルミ関税引き上げに始まり、今年5月まで4次にわたる対中関税引き上げ措置、昨年4月のZTEに対する米国内販売禁止、ファーウェイに対する露骨な圧力(カナダにおける2018年末のファーウェイ創業者の娘の逮捕、今年5月の米企業に対するファーウェイとの取引禁止命令など)が具体的な事例だ。詳細については今年4月から5月にかけて5回に分けて書いた米中新冷戦論(特に、5月12日付及び5月26日付)をご覧いただきたい。
米中貿易戦争が世界経済、ひいては日本経済に対して悪影響を与えることは言うまでもない。本来なら、トランプ主導の米中経済対立は日本にとって「迷惑」なものであるはずである。しかし、今のところ、その悪影響がなかなか顕在化してこない。米国の株式市場も(一時的に下げることはあっても)基本的には堅調さを保っている。日本経済も、決して良くはないものの、消費税対策の大規模財政出動が下支えしていることもあり、少なくともこれまでのところ、底割れする気配は見せていない。
多くの日本人にとって、トランプは自分たちが嫌いな中国に対して喧嘩を売り、中国を守勢に回らせているように見えているはず。しかも、米中経済対立の余波で日本経済が大打撃を受けるような事態には至っていない。日本人としては、安心してトランプを「日本に代わって中国を懲らしめる水戸黄門」に重ね合わせることができる。
これから
では、日本人のトランプ大統領に対する評価はこれからどう変わっていくのか?
まず、トランプが今後、日本に矛先を向ける可能性について。トランプが選挙戦で追い込まれ、対中政策などで成果が出ない状態が続けば、貿易や武器調達、防衛費増などで日本に過激な要求を突き付けてくる可能性は皆無ではない。しかし、安倍政権は米国の要求を早めの段階で聞き入れ、日米対立がトランプによって「劇場化」されるのを防いできた。安倍がトランプと闘うと決意しない限り、日本人がトランプに大きな反感を抱くきっかけはできにくい。
トランプがアメリカ・ファースト、すなわち自国の国益(より正確にはトランプにとっての国益)の追求を最優先する姿勢を変えれば、米国大統領に国際協調路線を期待する日本人のトランプ支持は大きく跳ね上がることになる。だが、もちろん、トランプがアメリカ・ファーストを捨てることはない。
一方で、米中の覇権争いが長期化することは必至だ。トランプ政権内には中国の台頭を抑えつけなければ米国の覇権が失われるという危機感を持った政策担当者が多い。トランプ自身も再選のために貿易面で中国と闘う姿を見せ続けようとするに違いない。もちろん、トランプには再選に向けて「成果」を出したと主張したい気持ちもあるだろう。その意味では、米中貿易戦争について近い将来、何らかの手打ちが行われても不思議ではない。しかし、米中蜜月を演じ続けることは、トランプの再選戦略上も、常に緊張と予測不能性を作り出して自らを主役の座に置き続けなければ気が済まない、というトランプ自身のディール・スタイルからも、あり得ない話。米中摩擦は、小康状態を挟むことはあっても長期的に続くと思っておくべきである。
米朝関係にも同じことが言える。トランプ政権が制裁を大幅に解除するのは、北朝鮮が核と中長距離ミサイルの開発をやめた時のみ。だが、それは北朝鮮にとって武装解除に応じることを意味している。金正恩が受け入れることはないだろう。かと言って、北朝鮮が核実験や中長距離ミサイルの発射といったトランプ政権のレッドラインを超えることも考えにくい。米朝関係も当面、現状維持が最もありそうなシナリオだ。
トランプは近い将来、日本人の嫌いな北朝鮮と中国との間で緊張状態を保ち続ける可能性が最も高い。そうだとすれば、日本人のトランプに対する評価は一定程度下支えされることとなろう。
日本におけるトランプ人気を左右する要因のうち、最も変動するのはトランプ再選の見通しかもしれない。4月末時点で46%まで上昇したトランプ大統領の支持率は、5月末時点では40%にまで低下した。党派色のないクイニピアック大学(コネチカット州)が6月11日に発表した世論調査の結果も、2020年の米大統領選挙でトランプ大統領は6人の民主党候補にリードを許している、というものであった。中でも、ジョー・バイデン前副大統領との差は13ポイントもあり、ミシガン、ペンシルバニア、テキサスなどの重要州でもトランプが後塵を拝していたと言う。トランプ陣営が行った別の調査でも、17州で壊滅的な数字が出たと伝えられている。
今後、トランプの支持率が下がって再選の見通しがきつくなるようなことがあれば、日本人がトランプに注ぐ目は厳しくなりそうである。長いものに巻かれるのも日本人によくある話なら、溺れる犬(政治家)を叩くのも日本人の特徴だからだ。
何が起こるか、見てみよう――。トランプ流に言えばこうなる。