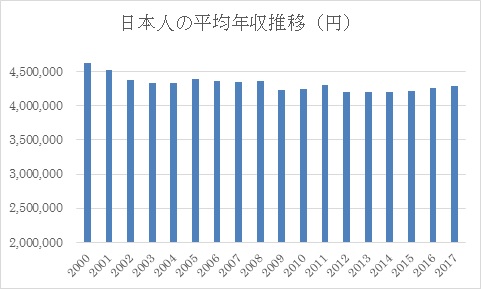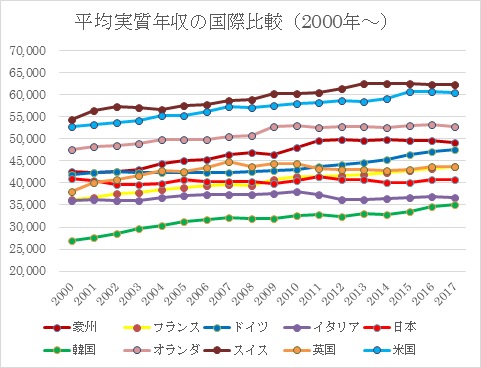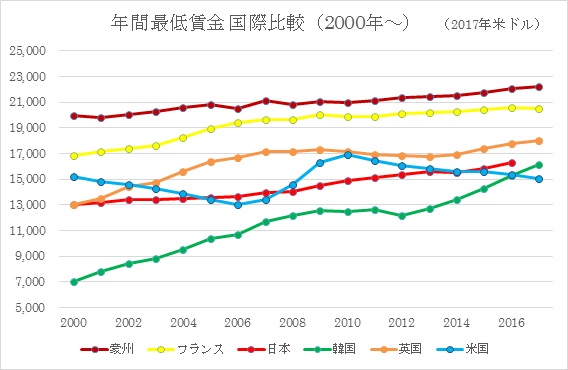もう旬を過ぎたようにも思えるが、横畠裕介内閣法制局長官の発言が物議を醸している。発言は、3月6日の参議院予算委員会で小西ひろゆき議員(無所属。参議院では立憲民主党の会派に所属)が質問に立っていた時に飛び出したものだ。
この種の話は切り取られて報道されることが多い。発言の前後の文脈を確かめる必要があると思い、議事録が出るのを待っていた。だが考えてみれば、国会が議事録を出す際には発言者等の「確認」をとる。横畠は自らの発言を撤回しているし、与党はこの問題の沈静化を図っている。ほとぼりが冷める前に議事録がホームページにアップされることは期待薄。我ながら迂闊だった。(3月15日現在、議事録はアップされていない。)
ただし、国会は議事録の形で活字にして記録を公表するのには慎重だが、動画ならそのまま垂れ流してくれる。少しタイミングが遅れてしまったが、件の発言の前後を動画で確認し、このポストを書くことにした次第である。
事の顛末
しきしまの 大和心のをゝしさは ことある時ぞ あらはれにける
発端は、この明治天皇御製の歌が安倍総理の施政方針演説(1月28日)に引用されていたことについて、小西が安倍総理にかみついたことだった。
この件について小西は1月31日に質問主意書を出している。日露戦争に際して大日本帝国憲法下の天皇が戦意高揚のために詠んだ歌を施政方針演説に引用し、「激動する国際情勢」に「立ち向か」い、「共に力を合わせ」ようと国会及び国民に呼び掛けたことは、憲法第九条の理念や「憲法前文の平和主義及び国民主権の理念に反する暴挙」だ、と小西は批判していた。
3月6日の予算委員会においても、小西は「とにかく戦意発揚でみんなで一致団結だ、と明治天皇の歌を詠みあげることは不適切だと思わないか?」と安倍に質した。これに対して安倍は、施政方針演説を読みあげながら小西の指摘するような意図を否定し、最後に「(小西の論理の)跳躍ぶりには驚くばかり」と苦笑交じりに答えた。(確かに小西の批判は無理筋であり、私も珍しく安倍に同情した。)
この答弁に小西は「安倍総理のように時間稼ぎをするような総理は戦後一人いませんでしたよ。国民と国会に対する冒涜ですよ。聞かれたことだけを堂々と答えなさい!」と声を荒げた。ただし、声を荒げたと言っても、切れたような感じはなかったし、「声の荒っぽさ」では与野党ともにもっと酷い議員はいくらでもいる。だが、年長の総理大臣に対して「答えなさい」と命令口調になったことについては、小西自身も「まずかったかな」という表情をしたように見えた。
そこで小西は、「私の質問は安倍内閣に対する監督行為です」と述べ、唐突に横畠内閣法制局長官を指名、「国会における国会議員の質問は国会の内閣に対する監督権の表れである」ことを確認するよう求めた。おそらく、国会議員(小西)の質問は内閣に対する監督権の行使だから、多少乱暴な言葉遣いをしても許される、と自己正当化したかったのであろう。その伏線として、2014年11月21日に小西が出した質問主意書に対する政府答弁書に「国会での審議の場における国会議員による内閣に対する質問は、憲法が採用している議院内閣制の下での国会による内閣監督の機能の表れである」と明記されていたことがあった。
いよいよ、横畠の発言が出てくる。逐語に近い形で引用してみたい。
(横畠)憲法上、議院内閣制でございまして、内閣は国会に対して責任を負う。その観点で国会が一定の監督的な機能、国権の最高機関、立法機関としての作用と言うのはもちろんございます。ただ、このような場で声を荒げて発言するようなことまで含むとは考えておりません。
ここで議場が騒然となり、審議が中断する。与党の理事が収拾を図り、横畠に再答弁を促したのち、審議は再開した。
(横畠)国会の監督権は委員であり、委員会、組織としての監督権でございまして、個々の委員の発言について述べたものではありません。先ほどの「声を荒げて」という部分については、これは委員会で適否について判断すべきことがらでございまして、私が評価すべきではありません。撤回します。
撤回はしたが、謝罪はなかった。もう一度、審議は中断し、再び横畠が答弁に立つ。
(横畠)委員会において判断すべき事柄について評価的なことを申し上げたことは越権であり、この点についてはお詫びして撤回させていただきます。
小西は撤回を受け入れると発言し、その場はこれで収まった。
何が問題だったのか?
では、横畠が取り消した発言、つまり、国会が内閣に対して果たす監督機能は国会で声を荒げて発言するようなことまでは含まない、という内容の発言は一体何が問題なのだろうか?
マスコミ報道や野党幹部の発言を見ると、横畠発言が議員を揶揄したとか、それが政治的発言だったことが問題視されているようだ。ここで「政治的発言」というのは、法制局の所管にかかわる行政技術上の見解ではないことを喋った、という程度の意味であろう。
横畠がニヤニヤしながら発言していたことを見ても、横畠の発言が小西を揶揄するものだったことは間違いない。しかし、小西が声を荒げて発言した――ただし、繰り返しになるが、この時の小西の発言は「声を荒げた」と言えるかどうか、微妙なものだった――ことに対し、それが国会の品位を貶める等の問題がある行為かどうかを評価するのは当該委員会や議院運営委員会である。横畠本人も認めたとおり、横畠が小西の発言を「声を荒げた」と評価したことは、法制局長官の職分とは関係のない「越権行為」ということになる。
横畠発言については与党議員からも批判の声があがった。与野党を問わず、議員心理の本音としては、法制局長官であっても官僚風情に国会議員が馬鹿にされた、ということが見過ごせなかったのであろう。
しかし、これだけなら、所詮は国会議員の見栄の問題にすぎない。国会という「コップの中の嵐」について、国会議員と一緒になって騒ぐのもくだらない。
だが、議員たちの薄っぺらい虚栄心から離れて横畠発言をありのままに読んでみると、単に官僚が国会議員を揶揄したということを超えた問題が浮き上がってくる。
それを説明するために、2014年11月21日に小西が出した質問主意書に対する政府の答弁書と3月6日の横畠発言を並べて見比べてみたい。
〈政府答弁書〉
国会での審議の場における国会議員による内閣に対する質問は、憲法が採用している議院内閣制の下での国会による内閣監督の機能の表れである。
〈横畠発言〉
憲法上、議院内閣制でございまして、内閣は国会に対して責任を負う。その観点で国会が一定の監督的な機能、国権の最高機関、立法機関としての作用と言うのはもちろんございます。(①)ただ、このような場で声を荒げて発言するようなことまで含むとは考えておりません。(②)
政府の公式見解(答弁書)は、国会質問は国会が内閣を監督する機能である、と明確に認めている。横畠発言の①も、(敢えて監督「的」という言葉を使ってはいるものの)政府答弁書のラインと基本的に齟齬はない。だが、②は違う。これによって横畠法制局長官は答弁書のラインに重大な限定をつけたことになる。
議員が国会で質問をするとしよう。答弁書のラインで行けば、プロ野球の優勝チームについての予想を聞いたりするのでない限り、政府に対する議員の質問内容は幅広く行政監督機能の一部とみなされ、質問の機会や質問内容の選択は保障されなければならない。
しかし、横畠発言を文字通りに読めば、どうなるか? 政府の憲法解釈、消費税引き上げ方針、あるいは森友・加計問題での総理夫妻や財務省の対応など、内容的には政府に対するチェック機能を果たすうえで当然正当な質問であっても、議員が声を荒げれば、正当な行政監督機能の行使とみなされない、と読めてしまう。政府の取り組みがひどい時、議員が声を荒げて質問することはよくある話だ。それを駄目だと言っていたら、国会の行政監督機能は空洞化する。
いくら小西がその前に頓珍漢な質問をしていたからと言っても、法制局長官の職にある者が感情に流され、国会の行政監督機能を不当に制約しかねない答弁をしてしまった――。横畠発言で一番問題なのはこの点だ。
横畠発言の背景
ではなぜ、横畠はこんなことを言ったのか? その背景についても少し考えておこう。
第一は、長期政権の驕り。野党や一部メディアの間では、横畠法制局長官が野党議員を揶揄するような発言をしたのは、安倍政権が6年以上続いて与党議員のみならず官僚までもが増長し、野党議員を軽んじているからだ、と憤る声が強い。確かに、そうした面はある。
与野党の力関係がある程度拮抗していれば、いくら高慢ちきな官僚でも、野党議員に対して好き勝手なことは言えない。衆参が捻じれていればもちろん、与野党が伯仲した状況で横畠発言が飛び出していれば、委員会の再開までに何時間かかっても不思議ではなかった。野党側が法制局長官の辞任を強硬に求めて審議拒否を続けでもすれば、国会日程が窮屈になって政府・与党が長官の首を差し出さなければならない――。そんな事態さえ、ありえた。
現実には、野党の弱体ぶりは目を覆うばかり。今回、横畠発言をめぐって委員会の審議は何分か止まった。だが、所詮はその程度のこと。官僚たちの間には、官邸と与党には一生懸命忖度する一方、野党は歯牙にもかけない雰囲気が間違いなくある。
第二は、横畠個人の驕り。私の個人的な印象では、横畠個人の驕りが横畠をしてあのようなことを言わせた最大の理由だと思う。自民党の伊吹文明元衆院議長が「少し思い上がっているんじゃないか」と語ったのは、私と同じ感覚かもしれない。
横畠は今や、権勢の絶頂にいる。横畠は安倍内閣の最優先テーマであった安保法制の立役者の一人だ。内閣法制局や防衛省、外務省などをまとめて9条解釈変更の理論的支柱をつくっただけではない。国会審議にあたっては野党議員の追及を「カエルの面に小便」のごとくはねのけ、安保法制の成立にこぎつけた。横畠はそれによって安倍に大きな恩を売った。
内閣法制局の内部では、横畠は組織を守った救世主のような存在でさえある。安保法制をつくるため、安倍は当初、外務省出身の小松一郎を法制局長官に据えた。安保法制を作るには、それまで歴代内閣法制局が営々と築き上げてきた憲法9条の解釈、要するに「集団的自衛権の行使は憲法上、認められない」という解釈を変更しなければならなかった。それを実行できるトップとして、安倍は小松を抜擢したのだ。それは法制局にとって、人事面で侵略を受けたような有事であった。ところが小松は病に倒れ、検察庁出身で法制局次長を務めていた横畠にお鉢が回ってくる。横畠は、組織防衛のために安倍の求める9条解釈の変更に協力した。
ただし、横畠は9条解釈を根底から変更するのではなく、従来の内閣法制局の解釈に接ぎ木をするようなやり方で集団的自衛権の限定的な行使を可能にする新解釈を作り出した。その意味では、高畠は法制局の伝統的な解釈を最大限守り、集団的自衛権の行使容認を安倍が当初思っていたよりも微温的なものにした、と言うこともできる。
いずれにせよ、安倍との関係においても、法制局内部においても、横畠の地位を脅かす要素は見当たらない。こうした状況に置かれれば、よほどの人徳者でない限り、人間は増長する。横畠はまさにそうなった。野党議員はもちろん、与党議員であっても、国会議員何するものぞ、というのが彼の感覚であろう。
ついでに言うと、小西ひろゆき議員のキャラクターにも横畠の発言を誘発した部分が多少なりともある。質問したのが小西以外の議員であれば、高畠があそこまで本性を現わすこともなかったに違いない。
この記事を書くに当たっては、小西が予算委員会で質問した録画を何度も見た。率直に言って、小西が展開する議論の流れを追うのは骨が折れた。彼の論理は往々にして独りよがりで極端、加えて飛躍が甚だしい。また、彼のホームページを覗いてみたら、質問主意書の数に驚かされた。過去6年強の間に200近く出している。一見、立派なことに見えるかもしれないが、その大半は思いつきや独りよがりに溢れており、政府の答弁書も形式論とすれ違いを繰り返しているに過ぎない。一生懸命なのは認めるが、人間的にもう少し成長しないとまずかろう。
議員の資質がどうであれ、国会議員が政府に対して行う質問に制約をかけるべきではない。ましてや、横畠が言ったように「声を荒げるかどうか」を基準にするなど、言語道断である。国会議員が情緒不安定で切れるのを見たり、何様気取りか知らないが偉そうに発言するのを聞いたりするのは、私も不愉快極まりない。しかし、それは権力側による言論封殺を防ぐためのコストと考えるしかない。今回の小西の場合は違うが、声を荒げた質問の中にも政府に対するチェック機能として必要なものはありえる。
最後に蛇足を一言。国会議員たる者、もう少し品位を保ったらどうか、と思う議員が少なくない。「ヤジは議場の花」などとうそぶいてチンピラまがいの罵詈雑言を浴びせる輩、国会質問を政府に対する質問ではなく、他の政党に対する誹謗中傷の場として利用する輩・・・。選挙で選ばれれば何でも許される、という理屈を私は認めない。